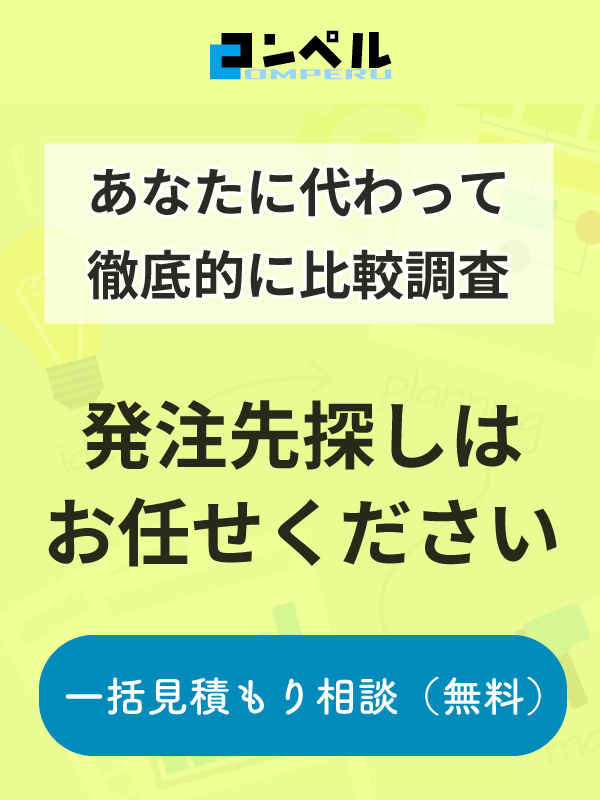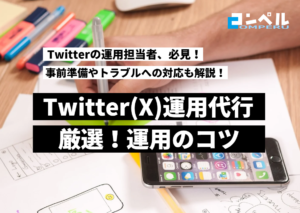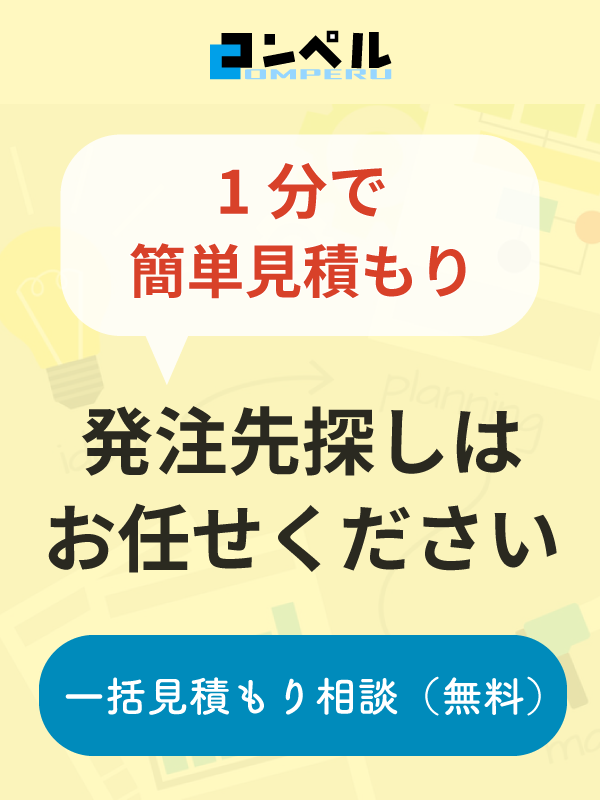「営業代行ってどれくらいの費用がかかるの?」「費用対効果はどうなの?」
営業負担を軽減し、成約率アップを目指したいけど、営業代行の費用や費用対効果が気になる方も多いのではないでしょうか?
営業代行の費用は、料金体系によって異なります。
一般的に、固定報酬型では月額50~70万円、成果報酬型ではアポイント1件あたり2万円~が相場です。複合型では、固定費と成果報酬を組み合わせた料金体系が一般的です。
この記事では、営業代行の料金体系や費用対効果、営業代行を選ぶポイントを解説します。
自社に最適な営業代行選びの参考になるでしょう。
営業代行の料金体系の特徴と費用相場
営業代行の料金体系は、成果によって費用が変わる「成果報酬型」と毎月一定額を支払う「固定型」、固定費と成果報酬を組み合わせた「複合型」など、さまざまです。
それぞれの料金体系の特徴と費用相場について解説します。
成果報酬
成果報酬型は、アポイント獲得数・受注数・売上額・営業活動の実績など、具体的な成果で費用が決まる料金体系です。
費用は、代行する業務内容や商材の特徴や難易度によって異なりますが、一般的に1件のアポイント獲得につき2~3万円、受注までを代行する場合には売上の30~50%程度が報酬の目安となります。
固定報酬
毎月一定の金額を営業代行会社に支払う料金体系です。
成果に関わらず、営業活動に従事するメンバーや、その活動を管理するスタッフの人数に応じて費用が決まります。
たとえば、「1人あたり月10万円」といったように、担当者の人数分を支払う形が一般的です。
複合型
固定費と成果報酬を組み合わせた料金体系です。
基本的な営業活動に対する報酬として、毎月一定額を支払うとともに、アポイント獲得や成約など、成果に応じて追加で払う費用が発生します。基本報酬は、完全固定型の営業代行費用の30〜60%程度が一般的ですが、取り扱う商品やサービス、業務範囲によって変動します。
成果報酬については、1件のアポイント獲得につき1~3万円程度の相場が多いですが、これも案件によって異なります。
営業代行の費用が高くなるケースとは?
料金体系や相場感はなんとなく見えてきたけれど、実際に依頼するとなると「どんな場合に費用が高くなるのか?」は気になるところです。
営業代行の費用は、商材の難易度や委託範囲、人材レベルなどによって変動します。
ここでは、費用が高くなりやすい代表的なケースを整理しておきましょう。
専門知識が必要な商材を扱う場合
医療機器や業務系ITソリューション、特化型SaaSなど、専門知識が求められる商材は、営業代行費用が高くなりやすい傾向があります。
なぜなら、顧客に正確かつ具体的な提案を行うには、業界知識や高度な提案力が必要になるからです。
特に以下のような商材は、理解や提案に専門的な背景知識が必要とされるケースが多くなります。
- 医療・製薬系の専門商材(例:検査機器、治療支援ツール)
- ERP(業務全体を一元管理する基幹システム)やMAツールなどのITソリューション
- 医療業界や建設業界など、特定業界に特化したSaaSサービス
上記のような商材は、顧客の業務課題に応じた丁寧なヒアリングや提案設計が必要となり、営業難易度が高いのが特徴です。
特にERPや金融系サービスのように導入ハードルが高い商材は、営業1件あたりの工数も大きく、単価も上がる傾向にあります。一方で、チャットツールや予約管理アプリのような汎用SaaSは、比較的導入が容易で、営業コストも抑えやすいでしょう。
自社の商材がどれほどの専門性を必要とするのか、事前に整理しておくことが大切です。
営業活動の全工程を委託する場合
営業のすべての工程を外部に委託する場合、営業代行の費用は高くなりやすくなります。
対応範囲が広がることで、必要な工数や人材の数が増えるからです。
単にテレアポだけを任せるのではなく、戦略設計からクロージングまで担ってもらうとなると、1社で複数人が関わる体制が必要になります。
営業代行における「全工程の委託」の主な内容は、以下のとおりです。
- ターゲットリストの作成
- 架電・メールなどのアプローチ活動
- アポイント調整・オンライン商談の実施
- 商談後のフォローアップ
- 契約書対応やクロージング業務
一括して依頼する「フルファネル型」は、月額100万円を超えるケースも珍しくありません。
特に、営業部門が未整備のスタートアップや、新規事業の立ち上げフェーズではこのタイプを選ぶ企業も多く、費用がかさみやすい傾向にあります。
ハイレベルな営業担当を指名する場合
経験豊富な営業担当者に対応してもらいたい場合、営業代行の費用は高くなる傾向があります。スキルや実績に応じて「プレミアム報酬」が設定されているケースが多いからです。
特に、大手企業での営業経験がある人や、特定業界に詳しいプロフェッショナルな人材は、高単価での契約となることが一般的です。
以下のようなケースでは、費用が高騰しやすくなります。
- 元大手企業のトップ営業に対応してもらいたい
- 建設・医療・金融など、専門業界に強い人材を希望する
- 経営層アポや高難度の商談を任せたい
上記のような人材は、営業代行会社でも限られた存在であり、スケジュールや契約条件に制約があることも少なくありません。
ただし、担当者の指名ができない会社もあるため、事前に確認しておくことも大切です。
自社の商材やターゲット層との相性を見極めながら、どこまでのスキルが必要かを見定めるようにしましょう。
料金体系別メリット・デメリット
営業代行の料金形態は、成果報酬・固定報酬・複合型などさまざまです。自社に合った料金体系を選ぶことが重要になります。
それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
成果報酬
メリット
成果報酬型営業代行のメリットは3つあります。
1.費用対効果が高い:成果が出た分だけ費用が発生するため、無駄なコストを抑えられる。また、短期的な試行も容易
2.成果が明確:アポイント獲得数や受注数など、具体的な成果で貢献度を測れる。効果的な評価が可能
3.効率的な営業が可能: アポイント獲得や受注といった成果に特化しており、効率的な営業が可能
デメリット
成果報酬型営業代行のデメリットは3つあります。
1.費用が変動しやすい:成果によって費用が大きく変動するため、予算管理が難しい
2.特定のサービスに偏る可能性:営業代行会社は、収益化しやすい案件に注力しがち
3.案件の質にばらつきが出る可能性:強引な営業や、顧客への説明不足など、案件の質に問題が生じる場合がある
固定報酬
メリット
固定報酬型営業代行のメリットは3つあります。
1.営業ノウハウの獲得:営業代行会社から、ターゲットリスト作成や営業トークなど、実務で役立つノウハウを提供してもらえる。特に、営業組織の立ち上げ期や、営業力強化を図りたい企業にとってメリットが多い
2.長期的な関係構築:同じ営業担当者が継続的に顧客と接するため、信頼関係を築きやすく、顧客との長期的な関係構築に繋がる。SaaSサービスなど、継続的な顧客との接点が重要な場合に特にメリットがある
3.安定した費用管理:毎月の費用が一定であるため、予算管理が容易。成果報酬型のように、費用が変動するリスクがない
デメリット
1.成果が出なくても費用が発生:成果が保証されないため、費用対効果が低いと感じる場合がある。契約前に、KPIや未達時の対応を明確にすることが重要
2.費用対効果が低い場合がある:サービスや目標によって、費用対効果が低くなる。特に、短期間で大きな成果を求める場合や、低単価なサービスの場合には注意が必要
3.案件数調整が必要になる場合がある:自社のリソースやサービスによっては、営業代行会社から供給される案件数を調整する必要がある
複合型
メリット
安定した稼働:月額固定費があるため、リスクに左右されず安定したサービスが受けられる
費用調整の柔軟性:固定費と成果報酬の割合を調整することで、予算に合わせてプランを選ぶことができる
リスクの軽減: 成果が出なくても、固定費のみで済むため、費用面でのリスクを軽減できる。固定費がある分、成果報酬額が安く設定されている
費用対効果を測る指標は?
CPA:顧客獲得単価
CPA(顧客獲得単価)とは、1人の新規顧客を獲得するためにかかる費用のこと。 簡単に言うと、「費用 ÷ 成果件数」で計算
例えば、広告代理店に400万円を支払って4,000人の新規顧客を獲得した場合、「400万円 ÷ 4,000人 = 1,000円」となり、CPAは1,000円になる
つまり、この広告代理店は、1人のお客様を獲得するために、平均1,000円のコストをかけている
CPAが低いほど、同じ費用でより多くのお客様を獲得できることを意味する。そのため、CPAは、広告の効果を測る上で重要な指標の一つとされている
CPO:受注一件あたりの獲得単価
CPO(Cost Per Order)は、1つの注文を獲得するためにかかる費用を示す指標。 つまり、広告費や人件費などの費用を、得られた注文数で割ることで計算される
例えば、ある商品を販売するために広告費として200万円を使い、その結果2,000件の注文を獲得した場合、CPOは「200万円 ÷ 2,000件 = 1,000円」となり、1件の注文を獲得するために1,000円かかったことになる
CPOが低いほど、同じ費用でより多くの注文を獲得できているということになる。そのため、CPOは、マーケティング活動の効率性を測る上で重要な指標として活用されている
ROI:投資利益率
ROI(Return on Investment)とは、投資した金額に対してどれだけの利益を得られたかを示す指標。 つまり、投資によって得られたリターンが、投資額に対してどれくらいの割合になるのかを表している
計算式は、(売上高 - 費用 - 投資額) ÷ 投資額 × 100 。 たとえば、500万円の投資を行い、3,000万円の売上高、500万円の費用が発生した場合、ROIは(3,000万円 - 500万円 - 500万円) ÷ 500万円 × 100 = 400%となる。これは、投資額に対して4倍の利益を得られたことを意味する
ROIを利用することで、営業代行サービスの導入効果を数値化し、その投資がどれだけの成果を生み出したのかを客観的に評価することができる。 ROIが高いほど、投資効率が良いと判断できる
営業代行会社を選ぶポイント
営業代行会社を選ぶ際の3つのポイントを解説します。
自社の目的に合った代行内容か?
営業代行会社によって、営業活動の代行範囲は大きく異なります。
アポ取りなどの初期段階の業務から契約まで、営業プロセス全体を請け負う「一気通貫型」のサービスを提供する会社もあるでしょう。一方で、テレアポなど、特定の業務に特化したサービスを提供している会社もあります。
自社で解決したい課題や、どの部分を代行したいのかを明確にして、それに合った代行会社を選ぶことが重要です。
各営業代行社の対応内容や実績をしっかりと比較検討すると、自社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。
実績はあるか
営業代行会社の実績をしっかりと確認しましょう。
ホームページや提案資料だけではなく、直接営業担当者に、過去の実績や成功事例について詳しく聞くことが大切です。
自社の業界や商品と似た案件を扱った経験があるかを確認すると、より具体的なイメージがつかめます。
実績の確認を行うと、その会社が自社案件の営業代行に向いているか確認できます。
費用対効果は高いか?
営業代行の費用対効果は、単純に料金だけのことではなく、獲得した見込み客や成約数といった成果とのバランスが重要になります。
見込み客創出コスト、商談創出コスト、顧客獲得コスト、LTVといった指標を用いて、費用対効果を測りましょう。
たとえば、固定報酬型と成果報酬型を比較する場合、アポイント数や成約率によって、どちらが費用対効果が高いか変わってきます。
自社の目標に合わせて、最適な料金体系を選びましょう。
営業代行を依頼する前にやっておくべきチェックリスト
営業代行をスムーズに進め、成果につなげるためには、依頼前の準備が欠かせません。
特に以下の4つの項目は、事前に整理しておくことで、無駄なコストやすれ違いを防ぎやすくなります。
| 目的と目標は明確か? | なぜ営業代行を使うのか、成果指標(KPI)はどう設定するかを整理 |
| 費用対効果の目安を想定できているか? | 想定単価を決めておくと、費用感のブレを防止 |
| どこまで外注し、どこを自社で行うか決めているか? | 役割分担を事前に決めておくことで連携もスムーズに |
| 成果をどう測り、どう改善していくかの体制はあるか? | モニタリング方法や、改善のフローを事前に設計 |
それでは、各項目について詳しく見ていきましょう。
目的と目標の明確化
営業代行を依頼する前に、まず「何のために依頼するのか」を明確にしておきましょう。
目的が曖昧なままだと、営業代行会社との認識にズレが生じ、成果にもつながりにくくなるからです。
「新規リードを獲得したい」「受注率を高めたい」「営業ノウハウを学びたい」など、目的によって適した戦略や体制は大きく変わります。
KPI(成果指標)も事前に設定しておくことで、進捗や成果の判断がしやすくなります。
目的・目標をセットで共有すれば、営業代行の効果を最大限に引き出せるようになるでしょう。
想定CPA・CPOのシミュレーション
営業代行を依頼する前に、CPA(顧客獲得単価)やCPO(受注単価)を事前にシミュレーションしておきましょう。
費用対効果の目安がないまま進めると、期待した成果が出ていても「費用が高い」と感じてしまったり、逆に赤字になるリスクもあるからです。
例えば「1件の受注に対していくらまでなら投資できるのか」を明確にしておけば、見積もりの妥当性や途中の判断がしやすくなります。
想定数値は、過去の実績や商談率、客単価などをもとに算出するのが基本です。
あらかじめ費用感の目安を持っておくことで、依頼後のミスマッチや損失リスクを減らすことができます。
委託する業務と内製する業務の線引き
営業代行を活用する際は「どこまでを外部に任せるか」「どこを自社で担うか」を明確にしておきましょう。
役割分担があいまいなままでは、連携ミスや責任の所在不明といったトラブルにつながりやすくなるからです。
特にリード獲得後の商談管理やクロージング、資料作成などは、どの業務を誰が行うのかを事前に整理しておくことが大切です。
例えば以下のように、業務を分解して考えるとイメージしやすくなります。
| 初期アプローチ(テレアポ、メール) | →営業代行に委託 |
| アポ取得後の商談・資料準備 | → 自社で対応 |
| 成果データの管理・改善提案 | → 双方で連携 |
役割を明確にしておくことで、営業代行との連携がスムーズになり、無駄なやりとりやコストのロスも防ぎやすくなります
成功条件とモニタリング体制の整備
営業代行を依頼する際は「何をもって成功とするか」をあらかじめ定義しておきましょう。
ゴールがあいまいなままだと、成果が出ているのか判断できず、期待とのギャップが生じやすくなるからです。
「アポイント獲得数」「受注件数」「商談化率」など、具体的な指標を設定しておけば、進捗の確認や改善の判断がしやすくなります。
あわせて、レポート形式や確認頻度、改善提案のタイミングなど、モニタリング体制もすり合わせておきましょう。
成果の判断基準と確認方法を整えておくことで、営業代行との連携をよりスムーズにできるでしょう。
営業代行に関するよくある質問
営業代行の料金について、よくある質問をまとめました。営業代行を検討する際の参考にしてください。
営業代行会社を使うメリット・デメリットは?
営業代行は、新規顧客獲得や人件費削減に有効ですが、自社で営業ノウハウを蓄積することが難しく、外部に依存してしまうリスクもあります。
メリット
・営業力不足の解消:プロの営業に任せることで、短期間で多くの顧客を開拓できる
・人件費削減:自社で営業チームを組むよりも、コストを抑えることができる
・専門知識の活用:さまざまな業界の営業経験を持つプロから、専門的な知識やノウハウを学ぶことができる
デメリット
・ノウハウ蓄積の遅れ:自社で営業活動を行わないため、営業のノウハウが蓄積されにくい
・外部への依存:営業代行会社に依存しすぎると、自社の営業力が低下する可能性がある
どちらを選ぶかは、自社の状況や目標によって異なります。
一定期間、営業代行を利用して実績を積み重ねてもらい、その後は自社でノウハウを蓄積するという方法も考えられます。
営業代行に向いている商材は何ですか?
営業代行は、どんな商材でも向いているわけではありません。
商材の特性によって、営業代行が効果的なケースとそうでないケースがあります。
高単価な商材は、1件の成約で得られる利益が大きいため、営業代行にかけたコストを回収しやすい傾向にあります。特に、専門的な知識や経験が必要な無形商品、たとえばソフトウェアやコンサルティングサービスなどは、営業代行の専門性を生かせる分野です。
顧客数が多く、1対1の営業活動が効果的な商材も、営業代行と相性が良いといえるでしょう。
低単価商品や有形商品、ニッチな市場向けの商品などは、営業代行よりも他のマーケティング手法が適している場合があります。
知名度が高い商材やSaaS、過去に実績のある商材などは、営業代行を活用することで、より効果的な営業活動が期待できます。
営業代行に向いている商材は以下の4つです。
・高単価で、専門的な知識が必要な無形商品
・顧客数が多く、1対1の営業活動が効果的な商品
・知名度が高く、SaaSのようなサブスクリプションモデルの商材
・営業代行会社が過去に実績のある商材
自社の商材がこれらの特徴に当てはまるか、一度検討してみましょう。
営業代行費用を抑えるには?
営業代行の費用を抑え、費用対効果の高い営業活動を行うには、3つの方法があります。
1. KPIと顧客獲得単価を明確にする
目標を明確にすることで、無駄な施策を削減できます。
営業代行に依頼する際は、自社商材のKPI(目標達成度を測る指標)を明確にし、目標達成までの期間や獲得件数を定めましょう。また、顧客獲得単価(CPA)を計測することで、費用対効果を測り、必要に応じて施策を見直すことができます。
2. 自社で営業戦略を策定する
営業代行費用を抑えるため、自社で営業戦略を策定することも可能です。
ただし、自社にリソースがない場合は、失敗するリスクも考慮しましょう。
3. 委託する人数や業務を絞る
必要な人数や業務を絞ることで、コストを削減できます。
自社の施策やKPIを見直し、どの業務にどれだけの人員が必要かを判断しましょう。
営業代行の費用を抑えるポイントをまとめると、
・目標を明確にする
・顧客獲得単価を計測する
・自社で営業戦略を策定する
・委託する人数や業務を絞る
これらの方法を組み合わせることで、営業代行費用を抑えられ費用対効果も高まるでしょう
まとめ
この記事では、営業代行の料金体系や費用対効果、そして営業代行会社を選ぶ際のポイントを解説しました。
営業代行の料金体系は、成果報酬型、固定報酬型、複合型などさまざまです。
それぞれの料金体系にはメリット・デメリットがあり、自社の状況や目標に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
費用対効果を測る指標としては、CPA(顧客獲得単価)、CPO(受注一件あたりの獲得単価)、ROI(投資利益率)などが挙げられます。これらの指標を参考に、どの営業代行会社を選ぶべきか検討しましょう。
営業代行会社を選ぶ際は、自社の目的に合った代行内容か、実績はあるか、費用対効果は高いかなどをしっかりと確認することが大切です。
この記事を、営業代行選びの参考にしてください。
営業代行をお探しなら『コンペル』
営業代行サービスは、自社の営業人員が足りないときや、新規顧客の開拓をスピードを上げるとき、営業力を強化しさらに営業効率を上げたい場合に便利なサービスです。自社の状況や目的に合わせて営業代行会社を探しましょう。
営業代行探しでお困りの方や、あまり時間や手間をかけられない方は、お気軽にコンペルにご相談ください!営業代行探しの専門アドバイザーが、あなたに代わってぴったりの会社をお探しいたします。ご利用料金はかかりません。
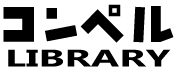
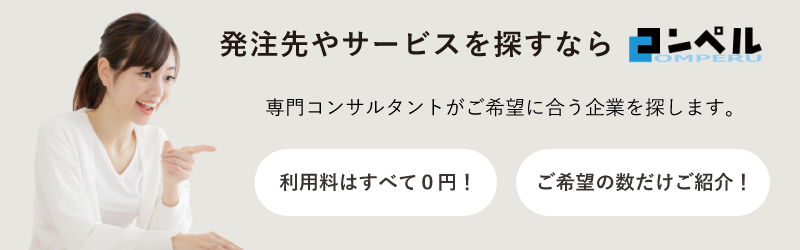

![プライマシー(初頭)効果とは -[ビジネス用語集]](https://comperu.jp/library/wp-content/uploads/2021/02/bizwords-150x150.jpg)