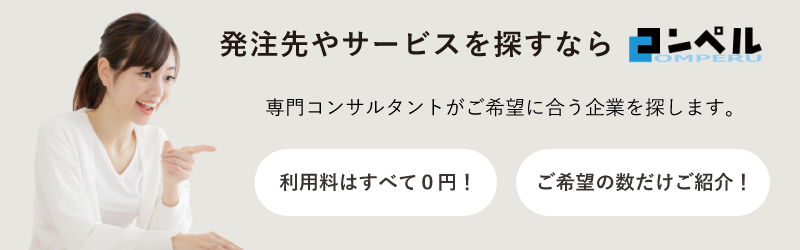営業代行サービスの活用は、商材選びによって成果が大きく左右されるため、十分な注意が必要です。
高単価や無形、知名度が高い商材は営業代行との相性が良く、効率的な売上拡大が期待できます。一方で、専門知識が必要な商材や低単価な商品は、営業代行では成果を出しにくい場合があります。
商材の特徴や自社の事業フェーズを見極めることが、営業代行活用の成否を分けるポイントです。
そこで今回は営業代行向けの商材とは何か、その特徴や見極め方、向かないケースについて解説します。ぜひ参考にしてください。
営業代行に向いている商材の特徴
営業代行を検討する際には、自社の商材が「営業代行に向いているか」を見極めることが大切です。
実は、営業代行に適している商材には、いくつか共通した特徴があります。
まずは、代表的な特徴を一覧で整理してみましょう。
| 特徴 | ポイント |
| 高単価・高利益率の商材 | 営業コストを回収しやすく、利益確保に向いている |
| 無形商材(SaaS、コンサルティングなど) | 在庫リスクがなく、提案営業に集中できる |
| ターゲットが明確なBtoB商材 | 見込み顧客リストが作りやすく、効率的なアプローチが可能 |
| 市場ニーズが高い商材 | 顧客の反応が良く、商談につながりやすい |
| 知名度がある商材 | ブランド力で初期段階から信頼を得やすい |
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
高単価・高利益率の商材
営業代行と相性の良い商材の一つは、高単価・高利益率の商材です。
営業代行を活用する場合、当然ながら人件費や運営コストがかかります。
そのため、1件の契約で得られる利益が小さいと、コストを回収できずに赤字になってしまうリスクが高まるからです。
逆に、高単価・高利益率の商材であれば、1件受注するだけでも十分にコストを上回る利益が見込めるため、営業代行を有効な手段として活用しやすくなります。
具体的には、以下のような商材が挙げられます。
- BtoB向けソフトウェア
- 大型設備
- コンサルティングサービス
上記商材は1件ごとの契約金額が大きく、利益率も高いため、営業代行によるアプローチが効果的です。
営業代行会社も、報酬体系に成果報酬型を採用しやすく、双方にとってメリットのある関係を築きやすい特徴があります。
無形商材
無形商材は、営業代行と相性が良いタイプの商材です。
物理的な在庫を持たない無形商材は、在庫管理や配送といった付帯業務が不要なため、営業活動に専念できる点からです。
顧客ごとにニーズに合わせた提案を行いやすく、提案営業を得意とする営業代行会社の力を最大限に引き出せるでしょう。
商品そのものの「モノ」としての比較が難しいため、営業担当者の提案力が成果に直結しやすい特徴もあります。
無形商材には、以下のような例があります。
- クラウドサービス(SaaS)
- ITソリューション
- 研修・コンサルティングサービス
ニーズに応じた提案型営業が効果的なため、営業代行会社がターゲット企業に対して柔軟なアプローチを仕掛けやすい分野といえます。
無形商材は提案営業との親和性が高く、営業代行を活用すれば効果的な新規開拓を実現しやすいでしょう。
ターゲットが明確なBtoB商材
ターゲットが明確なBtoB商材は、営業代行が良い商材です。
営業代行を活用する際には、誰に対して営業をかけるのかを明確にできるかが重要なポイントです。
ターゲットが具体的であればあるほど、見込み顧客リストを精度高く作成でき、効率的なアプローチが可能になります。
営業先が絞り込まれていることで、営業代行会社も短期間で成果を出しやすくなり、依頼する側にとっても費用対効果が高められるでしょう。
具体例としては、以下のような商材が挙げられます。
- 中小企業向けITツール
- 業務支援サービス
- 特定業界向けクラウドサービス
上記商材は、対象となる業種や企業規模が明確なため、ターゲットリストをもとに的確な営業活動を展開しやすい特徴があります。
ターゲットが明確なBtoB商材は、営業代行によるリスト作成とアプローチの精度が高まり、成果につながりやすいと言えるでしょう。
市場ニーズが高い商材
市場ニーズが高い商材は、営業代行と相性の良い商材の一つです。
営業代行を活用する上で重要なのは、顧客側に一定のニーズや関心が存在するかどうかです。
市場での需要が高い商材は、提案を受けた際の顧客の反応が良く、アポイント取得から商談成立までのプロセスがスムーズに進みやすくなります。
特に、時流に合ったテーマや社会課題に対応している商材は、営業代行の成果が出やすい傾向にあります。
具体的には、以下のような商材が挙げられます。
- DX支援サービス
- 業務効率化ツール
- リモートワーク支援システム
上記商材は、市場全体の関心が高まっている領域に位置しているため、ターゲット企業からの興味関心を引きやすく、営業代行による新規開拓にも効果的です。
市場ニーズが高い商材は、営業代行を活用する際に短期間で成果を上げやすく、戦略的な営業活動を後押ししてくれるでしょう。
知名度がある商材
知名度がある商材も、営業代行と相性の良い商材の一つです。
営業代行によるアプローチでは、初対面の相手に商材の魅力を伝え、短時間で信頼を得ることが求められます。
すでに市場で一定の認知度がある商材であれば、顧客の警戒心が低く、商談の初期段階からスムーズに話を進めやすくなるでしょう。
逆に、全く無名の商材だと、まず認知を広げるところから始める必要があり、営業難易度が一段と上がってしまいます。
具体例としては、以下のような商材が挙げられます。
- 有名ITベンダーのクラウドサービス
- 認知度の高い業務支援ツール
- マスメディアなどで紹介されたサービス
上記のような商材は、すでに市場で一定の評価を得ているため、営業代行でもスムーズに商談へとつなげやすい傾向があります。
知名度がある商材は、営業代行による新規開拓においても提案のハードルを下げ、成果につながりやすい重要な要素となるでしょう。
営業代行に向かない商材の特徴
営業代行は便利な手段ですが、すべての商材に向いているわけではありません。
商材の性質によっては、外部の営業代行会社を活用しても思ったような成果が出にくいケースもあります。
まずは、営業代行に向かない商材の特徴を一覧で整理してみましょう。
| 特徴 | ポイント |
| 利益率が低い商材 | 営業コストをカバーできず赤字リスクが高い |
| 高度な専門知識が必要な商材 | 短期間で営業に必要なスキルを習得するのが難しい |
| ターゲットがニッチすぎる商材 | 見込みリストが作りづらく、アプローチ対象が少ない |
| 対面営業・長期フォローが必須な商材 | 長期的な信頼構築が求められ、外部営業では対応しにくい |
それぞれの商材の特徴と順番に見ていきましょう。
利益率が低い商材
利益率が低い商材は、営業代行との相性が良くないケースが多いです。
営業代行を活用する場合には、外部リソースにかかる費用を含めたコスト負担を考慮する必要があります。
利益率が低い商材では、1件受注しても営業コストを回収できない可能性があり、結果的に赤字になってしまうリスクが高くなるからです。
営業代行側も成果報酬型の契約を敬遠する傾向があり、受託自体が難しくなるケースもあります。
具体例としては、以下のような商材が該当します。
- 安価な消費財
- 単発の小規模サービス
上記のような商材は、1件あたりの売上単価が低く、営業にかかるコストを補うのが難しいため、営業代行によるアプローチには適していません。
利益率が低い商材は営業代行の費用対効果を悪化させやすく、活用を検討する際には十分な注意が必要です。
高度な専門知識が必要な商材
高度な専門知識が必要な商材は、営業代行との相性が良くない傾向にあります。
営業代行を活用する場合、限られた期間内で商材の理解を深め、提案活動を行う必要があります。
しかし、特定の業界知識や専門的な技術理解が不可欠な商材の場合、短期間で十分なスキルを習得するのが難しく、営業活動自体が高いハードルになってしまうからです。
具体例としては、以下のような商材が挙げられます。
- 医療機器
- 特殊なエンジニアリング製品
- 法律・会計分野向けの専門ソリューション
上記のような商材は、正確な専門知識に基づく説明や提案が求められるため、一般的な営業代行会社では対応が難しいケースが少なくありません。
販売にあたって特別な資格や免許が必要な商材も、営業代行には適していません。
資格の取得には一定の学習期間が必要であり、誰でもすぐに営業活動に参加できるわけではないからです。
高度な専門知識や資格が求められる商材を営業代行に任せる場合は、専門特化型の代行会社を慎重に選ぶか、自社内での営業体制強化を検討しましょう。
ターゲットがニッチすぎる商材
ターゲットがニッチすぎる商材も、営業代行との相性があまり良くありません。
営業代行を活用するには、ある程度の規模感を持ったターゲット市場が必要です。
しかし、ターゲットが限定的すぎると、アプローチできる見込み顧客の母数が少なくなり、営業活動の効率が著しく低下してしまいます。
結果として、営業代行にかけたコストに対して成果が見合わず、費用対効果が悪化するリスクが高まります。
具体的には、以下のような商材が挙げられます。
- 特殊な産業用部品
- 業界特化型のニッチなITツール
- 特定条件下のみ使用される機器・システム
上記のような商材は、限られた業界や用途でのみ必要とされるため、ターゲット企業のリストアップやアプローチ活動に多大な労力がかかるケースが多くなります。
ターゲットがニッチすぎる商材の場合は、営業代行の効果を期待しすぎず、代替手段も含めた慎重な検討が求められるでしょう。
対面営業・長期フォローが必須の商材
対面営業や長期的なフォローが必須となる商材は、営業代行に不向きです。
営業代行は、基本的に短期的な成果を重視する傾向があります。
しかし、対面での関係構築や、数カ月〜数年単位で信頼関係を育てながら提案を進めるタイプの商材では、担当者の継続性や深いコミュニケーション力が求められます。
外部委託の場合、担当変更や情報伝達のズレが生じやすく、顧客との長期的な信頼構築が難しくなるリスクが高いといえるでしょう。
具体例としては、以下のような商材が挙げられます。
- 大型システムの導入プロジェクト
- 長期契約を前提としたBtoBサービス
- 高額な設備投資が必要な商材
上記のような商材は、導入前後で密なやり取りが続くことが多く、社内の専任担当者が顧客に寄り添いながら対応する体制が必要です。
対面営業や長期的な信頼構築が求められる商材では、営業代行に頼りすぎず、社内で一貫した営業体制を整える方が良いでしょう。
アポ取りなどの一部業務だけを代行するのも、一つの方法です。
自社商材が営業代行に向いているかを見極めるポイント
営業代行を検討する際には、自社の商材が本当に営業代行に向いているかを冷静に見極めることが大切です。
勢いだけで依頼してしまうと、成果につながらず、かえってコストだけが膨らんでしまうリスクもあります。
まずは、判断すべきポイントを確認しておきましょう。
営業代行に向いているかを判断する主なポイントは、以下のとおりです。
- 単価・利益率から見る
- ターゲット市場の広さから見る
- セールスプロセスの複雑さから見る
- LTV(顧客生涯価値)で考える
それぞれの判断のポイントを確認していきましょう。。
単価・利益率から見る
向いているかを判断するポイントの一つは、単価・利益率から見ることです。
営業代行を活用する際には、一定のコストが発生します。
そのため、1件の契約で得られる利益が営業コストをしっかり上回るかどうかが大きな判断基準になります。
具体的な目安としては、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 1件受注あたりの粗利が営業代行コストを大幅に上回ること
- 粗利率30%以上が一つの目安
- 継続契約やアップセルの可能性があればさらに好条件
上記基準を満たしていれば、営業代行による新規開拓でも十分な費用対効果を期待できるでしょう。
営業代行を成功させるためには、単価と利益率を事前にしっかりと見極めることが欠かせません。
ターゲット市場の広さから見る
ターゲット市場の広さは、自社商材が営業代行に適しているかを判断するうえで欠かせないポイントです。
営業代行を効果的に活用するためには、アプローチできる企業や顧客の母数がある程度確保できている必要があります。
市場が極端に狭いと、リスト作成や営業活動に限界が生じ、期待した成果を上げるのが難しくなってしまうからです。
特に、ニッチ市場や特殊用途向けの商材では、営業代行との相性に注意が必要です。
具体的な目安としては、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 目安として数千社以上のターゲットが存在していること
- 業種・規模などでリストを絞り込んでも一定数残ること
- 市場自体が縮小傾向ではなく、成長性が見込めること
上記のポイントを満たしていれば、営業代行によるリスト作成・アプローチが効率的に進みやすくなります。
営業代行を検討する際は、ターゲット市場の広さと成長性を事前に確認しておく必要があります。
セールスプロセスの複雑さから見る
セールスプロセスの複雑さも、自社商材が営業代行に適しているかを判断する上で大切な要素です。
営業代行は、短期間でアポ獲得や商談化を目指すスタイルが一般的です。
しかし、セールスプロセスが複雑すぎると、外部の営業担当者が商材を完全に理解しきれず、スムーズに提案・クロージングまで持ち込むことが難しくなります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 商材説明に時間がかかり、複雑な技術解説が必要
- 決裁者が複数存在し、社内調整に時間がかかる
- デモやトライアルが必須で、成約までに工程が多い
上記の条件が重なる場合、営業代行では対応が難しくなる可能性があります。
営業代行を検討する際には、自社商材のセールスプロセスがシンプルで提案しやすいかどうかも、あらかじめチェックしておきましょう。
LTV(顧客生涯価値)で考える
自社商材が営業代行に向いているかを判断する際には、LTV(顧客生涯価値)も考慮しましょう。
LTV(顧客生涯価値)とは、「一人の顧客が取引期間中にもたらす総売上」のことを指します。
単発の売上だけではなく、長期的な取引によって積み上がる価値を測る指標です。
営業代行を活用する際、初回の受注だけで費用を回収しようとすると、単価や利益率に大きな負担がかかります。
しかし、受注後に長期的な取引が見込める場合、初期コストを補うだけではなく、継続的な利益を得られるでしょう。
特に、サブスクリプション型サービスやリピート購入が前提のビジネスモデルでは、LTVが高いほど営業代行活用のメリットが大きくなります。
具体的には、以下のような商材が挙げられます。
- 月額課金型のクラウドサービス(SaaS)
- 定期購入が前提の業務用消耗品
- 保守・メンテナンス契約が付帯する製品
上記のような商材は、一度契約を獲得すれば長期間にわたって売上が積み上がるため、営業代行にかかる初期コストを十分に回収できる可能性が高くなります。
営業代行を検討する際には、初回売上だけではなくLTVまで含めた視点で自社商材を評価する必要があります。
営業代行を活用するメリット5つ
営業代行を活用するメリットには、大きく次の5つが挙げられます。
- コストを削減できる
- 専門スキルやノウハウを活用できる
- 新規顧客獲得や売上拡大が期待できる
- 自社リソースの有効活用と業務を効率化できる
- 柔軟な対応に期待ができる
それぞれ解説します。
1.コストを削減できる
営業代行を活用する最大のメリットは、営業人員の採用や教育、固定費となる人件費を抑えられる点です。
自社で営業チームを構築する場合、給与や社会保険、福利厚生など多くのコストが発生しますが、営業代行を利用すれば必要な分だけ外部リソースを活用でき、無駄なコストを削減できます。
特にスタートアップや中小企業にとっては、限られた予算内で効率的に営業活動を展開できるため、事業の成長スピードを加速させることが可能です。
2.専門スキルやノウハウを活用できる
営業代行会社は、営業活動に特化した専門家が在籍しており、豊富な経験と実績に裏打ちされたノウハウを持っています。
自社だけでは得られない最新の営業手法や業界知識を活用できるため、より効率的かつ効果的な営業戦略の実行が可能です。
これにより、リード獲得からクロージングまで一貫した高品質な営業活動が実現し、成果につながりやすくなります。
3.新規顧客獲得や売上拡大が期待できる
営業代行を導入することで、短期間で新規顧客の獲得や売上の増加が期待できます。
営業リソースが不足している場合でも、外部の専門チームが積極的にアプローチを行うため、これまでリーチできなかったターゲット層への営業が可能です。
実際に、営業代行導入後に新規顧客が倍増し、売上が前年比で大幅に向上した事例も多く報告されています。
4.自社リソースの有効活用と業務を効率化できる
営業活動を外部に委託することで、社内の人材や時間をコア業務やプロダクト開発、顧客サポートなどに集中させることが可能となります。
これにより、全体の業務効率が向上し、企業全体の生産性アップにつながります。特に、限られた人員で多くの業務をこなす必要がある中小企業やスタートアップにとって、大きなメリットです。
5.柔軟な対応に期待ができる
営業代行は、市場環境や事業フェーズの変化に応じて、必要なタイミングで営業活動の規模を拡大・縮小できる柔軟性があります。
新規事業の立ち上げや繁忙期には営業リソースを増やし、落ち着いた時期には縮小するなど、状況に応じた最適なリソース配分が可能です。このスケーラビリティにより、無駄なく効率的に営業活動を展開できるでしょう。
営業代行を活用する際の注意点
営業代行を活用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 目標の設定とKPIを明確化する
- 適切なパートナーを選ぶ
- 業務範囲と期待成果を明確化する
- 情報共有とコミュニケーションを徹底する
- 効果測定と改善のサイクルを構築する
それぞれ解説します。
1.目標の設定とKPIを明確化する
営業代行を活用する際は、事前に具体的な目標やKPIを設定することが不可欠です。なぜなら、目標受注数やアポイント獲得数、CPAやCPOなどの指標を明確にすることで、営業代行会社と自社が同じ方向を向いて活動できるからです。
曖昧な目標では進捗管理や成果評価が困難になり、期待した効果が得られないリスクが高まります。そこで、現実的かつ挑戦的な目標を設定し、進捗を定期的に評価することで、営業活動の質と成果を最大化しましょう。
2.適切なパートナーを選ぶ
営業代行会社の選定は、成果を大きく左右する重要な要素です。自社の業種やニーズに合った実績豊富なパートナーを選ぶことで、より効果的なアプローチや戦略を実施でき、高いROIが期待できます。
適切なパートナー選びでは、信頼性や過去の実績、専門性を事前に確認し、複数社を比較検討することが重要です。もし不適切な業者を選んでしまうと、期待した成果が得られず、コストだけがかかってしまうリスクが高まります。
3.業務範囲と期待成果を明確化する
営業代行に依頼する業務範囲や期待する成果を事前に明確にしておくことが重要です。なぜなら、クロージングまで任せるのか、アポイント取得のみなのかなど、具体的な役割分担を双方で認識しておくことで、ミスコミュニケーションやトラブルを防げるからです。
業務範囲が曖昧だと、受注率向上のための施策も打ち出しにくくなり、成果の最大化が難しくなります。
4.情報共有とコミュニケーションを徹底する
営業代行会社との密な情報共有と定期的なコミュニケーションは、成果を高めるために欠かせません。ターゲットリストや過去の受注事例、サービスの強みなど、必要な情報を整理し、営業代行会社と共有することで、アプローチ戦略の精度が向上します。
そこで、進捗報告や改善提案の機会を設け、課題があれば迅速に対応する体制を整えることが大切です。
5.効果測定と改善のサイクルを構築する
営業代行の成果を最大化するには、定期的に効果を測定し、必要に応じて改善策を講じるサイクルを構築する必要があります。
営業データの収集と分析を行い、KPIの達成状況や課題を把握することで、次の戦略立案や施策のブラッシュアップが可能です。
データに基づく評価と改善を繰り返すことで、営業活動の効率と成果を継続的に高めることができるでしょう。
営業代行商材選びでよくある質問Q&A5選
以下では、営業代行商材選びでよくある質問をQ&A形式で5つ紹介します。
Q1.営業代行に向いている商材の特徴は何ですか?
A1.営業代行に向いている商材は、高単価で利益率が高いものや、無形サービス、継続契約が見込める商材が挙げられます。市場での認知度が高く、営業プロセスが標準化しやすい商品も適しています。逆に、低単価や大量販売が必要な商材、専門知識が必要なものは成果が出にくい傾向があります。
Q2.営業代行会社選びで重視すべきポイントは?
A2.営業代行会社を選ぶ際は、自社商材との相性や過去の実績、得意分野を必ず確認しましょう。BtoBやBtoC、業界特化型など会社ごとに強みが異なります。また、導入企業数や成功事例、クライアントの声なども参考にし、信頼できるパートナーかどうかを見極めることが重要です。
Q3.料金体系にはどのような種類がありますか?
A3.営業代行の料金体系には、固定報酬型、成果報酬型、ハイブリッド型があります。固定報酬型は月額費用が一定で安定した営業活動が可能、成果報酬型は成果ごとに費用が発生し初期費用を抑えやすいのが特徴です。自社の予算やリスク許容度に応じて最適な契約形態を選びましょう。
Q4.営業代行に向かない商材はどんなものですか?
A4.利益率が低い商材や、BtoC向けで大量販売が必要な商品、属人性が高いサービスは営業代行には向きません。また、アポ獲得から受注までの期間が長いものや、高度な専門知識が求められる商材も成果が出にくい傾向があります。自社商材が該当しないか事前に確認しましょう。
Q5.営業代行導入前に確認すべきことは何ですか?
A5. 営業代行導入前には、自社の営業課題や目標、ターゲット顧客を明確にし、商材の特性や営業手法が代行会社と合っているかを確認しましょう。また、契約内容や料金体系、成果報告の頻度、サポート体制なども事前にしっかりとチェックし、トラブルを防ぐために細部まで合意しておくことが大切です。
まとめ|営業代行に向いている商材を理解し、適切に依頼しよう
営業代行に向いている商材には、いくつか共通する特徴があります。
高単価・高利益率であること、無形商材であること、ターゲットが明確であること、市場ニーズが高いこと、そして知名度があることなどが挙げられます。
一方で、すべての商材が営業代行に適しているわけではありません。
低単価な商材、ニッチ市場向けの商材、高度な専門知識を必要とする商材などは、慎重な判断が求められます。
自社商材について「単価」「利益率」「ターゲット市場」「セールスプロセス」「LTV(顧客生涯価値)」といった観点から冷静にチェックすれば、営業代行を活用するかどうかを見極められるでしょう。
商材の特性を正しく理解したうえで、最適な営業代行会社を選ぶことができれば、成果につながる確率を高めることができるでしょう。
業者探しにあまり時間や手間をかけられない方や、依頼をお急ぎの方は、お気軽にコンペルにご相談下さい!営業代行探しの専門アドバイザーが、あなたに代わってぴったりの会社をお探しいたします。ご利用料金は無料です。