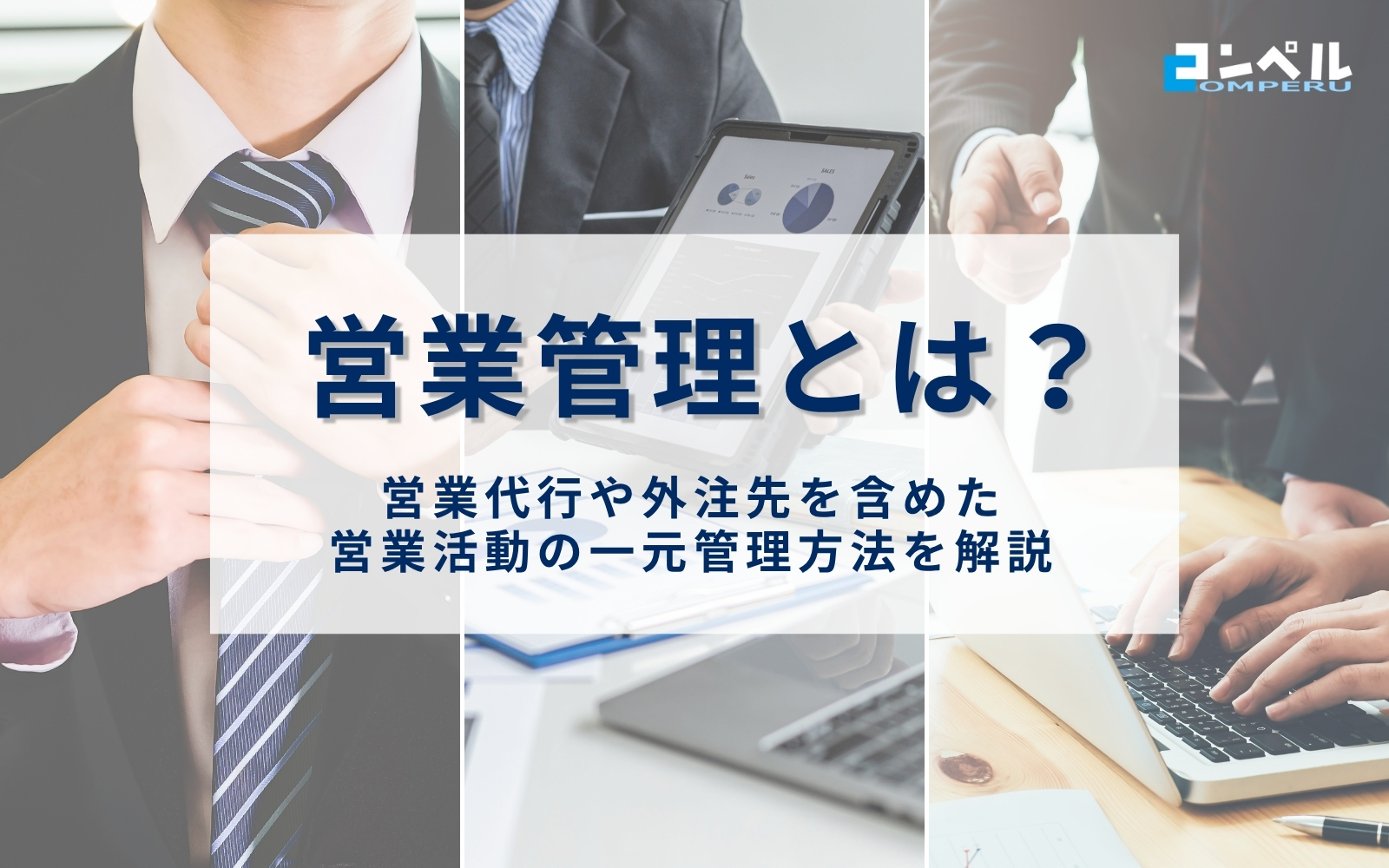業務委託契約書で営業代行を依頼したいと考えているものの「契約書って必須?」「どんな項目が必要?」と不安に感じていませんか?
営業代行では業務内容や成果の定義、報酬条件などを明確にしないと、認識のズレによるトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、営業代行における業務委託契約書の基本的な考え方や契約の種類、契約書に記載すべき内容、注意点を依頼者の視点からわかりやすく解説します。
安心して営業代行を進めるために、契約書の基礎を押さえておきましょう。
営業代行を依頼する際は業務委託契約書の締結は必須?
営業代行の依頼に契約書は絶対必要なわけではありませんが、トラブルを防ぐためにも、実際には契約書を交わすのが一般的です。
契約自体は「当事者の合意」で成立するため、書面がなくても法的には問題ないケースもあります。
ただし、営業代行のように報酬や成果、業務範囲などを取り決める業務では、口頭の合意だけではトラブルの原因になりがちです。
例えば「想定以上に高額な請求を受けた」「アポイントの質が伴っておらず成果と認めにくい」といったケースでは、報酬支払いをめぐるトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、契約書によって業務の内容や報酬条件、期間などを明確にし、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
営業代行をスムーズかつ安心して任せるためにも、契約書の締結は実質的には必要と考えておきましょう。
営業代行を依頼する際は業務委託契約書の締結は必須?
前章でもお伝えした通り、営業代行を依頼する際には契約書を交わすのが一般的です。
その理由は、大きく分けて法的リスクの回避と業務上のトラブル防止の2つにあります。
ここでは、それぞれの観点から契約書が必要とされる背景を解説します。
法的リスク回避
営業代行を依頼する際に契約書が必要とされる大きな理由のひとつは、法的なトラブルを回避するためです。
一見シンプルな業務でも、契約内容が曖昧だと、知らぬ間に法律違反や不利な立場に立たされるリスクがあります。
特に注意すべき法的リスクは、以下の3つです。
| 労働者性の認定 | 指揮命令系統が明確でない場合、委託先を実質的な従業員とみなされ、労働法が適用される可能性がある |
| 下請法の適用 | 発注者が資本金1,000万円超、中小の営業代行業者に委託した場合、報酬未払いや不当な条件変更は法律違反となる |
| 責任の所在が不明確 | トラブル時に「誰がどこまで対応すべきか」が曖昧で、損害賠償や業務遅延の責任が揉める要因になる |
契約書を交わさずに営業代行を依頼すると、知らず知らずのうちにリスクを抱えることになりかねません。
業務範囲や報酬条件、責任の明確化を契約書に盛り込んでおくことが、後のトラブルを防ぐために必要です。
口約束では危険
営業代行の依頼を「信頼してるから口頭で大丈夫」と済ませてしまうと、報酬や業務範囲に関する認識のズレから、金銭的な損失や信頼関係の破綻を招く可能性があります。
例えば、以下のようなケースに気を付けましょう。
- 「成果はアポイント取得のことだと思っていたのに、先方は成約が成果と解釈していた」
- 「メール送信も業務に含まれていると聞いたのに、対象外とされて追加請求された」
契約内容の食い違いでトラブルになる例は少なくありません。
こうした事態を防ぐには、事前に合意した条件を文書に残すことが何より大切です。
契約書が証拠となり、万が一のトラブルでも自社の正当性を証明できます。
営業代行を安心して任せるためには、「信頼関係だけに頼らない」備えが欠かせません。
業務委託契約の種類
営業代行を依頼する際に交わす契約は「業務委託契約」としてまとめられるのが一般的です。
ただし、業務委託といっても実際には「請負契約」や「準委任契約」など、法的な分類がいくつか存在します。
契約形態によって、業務の成果に対する責任の範囲や、報酬が発生するタイミングが異なるため、自社に合ったタイプを理解しておくことが大切です。
ここでは営業代行でよく使われる契約形態について、それぞれの違いを解説します。
請負契約
営業代行の業務委託で「成果報酬型」を選ぶ場合は、多くがこの請負契約にあたります。
請負契約とは、依頼主が成果に対して報酬を支払う契約形態であり、成果が出なければ原則として報酬は発生しません。
例えば、営業代行では「アポイントの獲得」「成約」「商品の受注」など、明確な成果に対してのみ報酬が支払われる形が一般的です。
ただし、成果物の定義が曖昧だとトラブルになりやすいため、契約書には何をもって成果とするかを必ず明記しておく必要があります。
成果が出たかどうかで報酬が決まるため、請負契約を結ぶ際には、成果の条件・納品期限・修正義務の範囲なども含めて、事前のすり合わせておきましょう。
参考:国土交通省「請負契約とその規律」
準委任契約
営業代行におけるもうひとつの代表的な契約形態が「準委任契約」です。
これは、依頼された業務の遂行自体が目的となる契約であり、必ずしも成果を上げる必要はありません。
例えば、マーケティング支援や営業戦略の設計、インサイドセールスの立ち上げといった業務は、実行されたかどうかが報酬発生の基準になるため、準委任契約に該当します。
なお営業代行では、準委任契約の中でもテレアポ件数やアポイント数などに応じて、基本報酬+成果報酬を取るケースもあります。
「業務は遂行するけど、成果が出た場合には追加で報酬を支払う」といったハイブリッドな運用も可能です。
似た名称に「委任契約」がありますが、これは弁護士や税理士など士業に適用される契約であり、営業代行ではあまり使われません。
本記事では、ここまで紹介した請負契約と準委任契約をまとめて「業務委託契約」と表現しています。
業務委託契約でかわす契約書は主に2種類
営業代行を業務委託する際には、契約内容を明文化するために契約書を取り交わすのが一般的です。
契約書には、大きく分けて「業務委託基本契約書」と「個別契約書」の2種類が存在します。
基本契約書は、すべての業務に共通するルールや条件を定めるもので、土台となる全体的な枠組みを示します。
一方、個別契約書は、案件ごとの具体的な業務内容や成果条件、報酬額などを詳細に記載するものです。
どちらも片方だけでは不十分で、両方をセットで取り交わすのが一般的な運用です。
ここでは、それぞれの契約書の特徴と押さえておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。
業務委託基本契約書|すべての業務に共通するルール
営業代行を依頼する際、まず整えておきたいのが「業務委託基本契約書」です。
基本契約書は、すべての案件に共通する基本的なルールを定める契約書であり、トラブルを未然に防ぐうえで欠かせない存在です。
業務内容や報酬、契約期間、秘密保持、損害賠償といった業務委託の根幹に関わる項目を網羅的に定めておくことで、後から発生しがちな認識のズレや責任の所在の曖昧さを回避できます。
例えば、業務中に起きたトラブルに関して「誰がどこまで責任を負うのか」が明記されていなければ、紛争につながる可能性もあります。
「個別契約書」と連動させる形で運用されることが多く、基本契約があることで、個別契約をスムーズかつ安心して結べるメリットもあります。
必ず目を通し、自社にとって不利な条件がないかをしっかり確認しておきましょう。
基本契約書の必須項目
営業代行の基本契約書には、業務全体に共通する重要な取り決めを記載しておく必要があります。
これは単なる形式ではなく、契約の目的や報酬の支払い条件、トラブル時の対応ルールなどを明文化し、双方の信頼関係を支える土台となります。
以下の項目は、業務委託基本契約書に盛り込むべき基本的な内容です。
|
上記項目をあらかじめ明文化しておくことで、万が一トラブルが起きた際にも、スムーズな対応が可能になります。
営業代行に安心して任せるためにも、基本契約書の内容は必ずチェックしておきましょう。個別契約書
営業代行の契約では、基本契約書に加えて「個別契約書」を交わすのが一般的です。
個別契約書とは、実際に依頼する営業業務の内容や報酬条件などを、案件ごとに具体的に取り決めるための契約書です。
基本契約書が「全体のルール」を定めるのに対し、個別契約書は「その都度の取引内容」を詳細に記すもので、一方だけでは契約内容が不完全になる恐れがあります。
例えば、訪問先の企業名やサービスの種類、1件あたりの報酬金額、支払いスケジュール、成果の定義(例:アポ獲得or成約)などは、すべてこの個別契約書に明記されます。
報酬成果連動型である場合は、特に「成果の基準」を曖昧にせず、明確にしておくことがトラブル防止のためには必要です。
しっかりと中身を確認・調整してから締結するようにしましょう。
個別契約書の必須項目|業務内容や報酬条件を明確にしてトラブル回避
個別契約書には、具体的な取引内容をきちんと記載する必要があります。
業務委託基本契約書が「全体のルール」だとすれば、個別契約書はその都度の業務内容や条件を明記するための詳細設計書ともいえます。
以下は、個別契約書に盛り込むべき主な項目です。
|
上記内容をを事前に明文化しておくことで、「報酬の支払い条件に食い違いがあった」「どこまでが業務範囲なのか不明確だった」といったトラブルを防げます。
なお、基本契約と個別契約の両方を締結する場合は、どちらが優先されるかを記載しておくことも必要です。
小規模な取引であれば、請書や注文書で済む場合もあるため、契約書の形式は業務内容に応じて柔軟に選びましょう。
基本契約と個別契約の関係性と優先順位
営業代行の契約では、基本契約書と個別契約書の両方を取り交わすのが一般的です。
2つの契約書は役割が異なるため、内容に矛盾や重複が生じることもあります。
だからこそ、どちらを優先するかを明記しておく必要があります。
通常、優先されるのは「業務委託基本契約書」です。
これは、全体のルールや共通事項を定めた契約であり、ベースとなる取り決めが記載されているからです。
一方、個別契約書は案件ごとの業務や報酬の詳細を記した書類であり、特定の取引に特化した内容が記載されます。
例えば、基本契約書では「成果報酬は1件1万円」と記載されていても、個別契約で「今回は1件8,000円で対応」と異なる記述があった場合、優先順位が曖昧だとトラブルに発展する可能性があります。
行き違いを防ぐには、契約書の中であらかじめ「契約内容に矛盾があった場合は基本契約書を優先する」など、明確な整合ルールを設けておくことが鉄則です。
契約書の優先順位はあいまいにせず、双方で認識をそろえておきましょう。
簡易な書面で済むケースと正式契約が必要なケースの見極め方
営業代行を依頼する際、必ずしも分厚い契約書を交わす必要はありません。
取引の規模や内容によっては、請書や注文書などの簡易な書面だけでも十分な場合もあるからです。
例えば、短期間で終了する単発の業務や、あらかじめ取引実績があり信頼関係が構築されている場合などは、注文書や合意メールだけで済ませるケースもあります。
一方で、成果報酬型の契約や、報酬額が大きく責任範囲も広い業務では、万が一のトラブルに備えて正式な業務委託契約書を交わすのが望ましいです。
判断の目安としては、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 取引金額が大きい/継続性がある
- 成果報酬などの不確定要素を含む
- 担当者の入れ替わりが予想される
- 機密情報の取り扱いが含まれる
- 法的リスクを最小限にしたい
契約書の形式は一律ではなく、業務の性質に応じて柔軟に選ぶことが大切です。
ただし、トラブル回避や責任の所在を明確にするためには、重要な取引ほど正式な契約書の締結をしておくと良いでしょう。
営業代行の業務委託契約書でテンプレート使用は可能?
営業代行の契約書を作成する際「テンプレートをそのまま使ってもいいのか?」と悩む方は多いかもしれません。
結論から言うと、テンプレートは参考にはなりますが、状況に応じた調整が必要です。
なぜなら、営業代行の契約内容は業種や成果条件、報酬形態などにより異なります。
テンプレートをそのまま使うと、自社の実情と合わず、重要な項目が抜けていたり、責任範囲が曖昧なまま進んでしまったりする場合もあるからです。
例えば、成果報酬型の場合には「成果の定義」や「成果未達時の扱い」、情報共有の範囲などを明記しないと、後々トラブルにつながるリスクがあります。
どうしても見本が必要な場合は、厚生労働省が公開している業務委託契約の参考例などをベースに、自社に合った形にカスタマイズするのが安心です。
参考:厚生労働省「契約書の参考例」
自社での作成が無理な場合は専門家へ依頼
営業代行の契約書は、法的な知識や実務経験がないと不備が生じやすく、自社で完結するのが難しいケースも少なくありません。
特に、成果報酬型や情報管理に関わる契約は、トラブルの芽を事前に摘むための正確な文言や構成が不可欠です。
そこで有効なのが、契約書作成に精通した専門家への依頼です。
それぞれの専門家の特徴を確認しておきましょう。
| 弁護士 |
|
| 社会保険労務士(社労士) |
|
| 行政書士 |
|
例えば「業務内容の定義があいまいで、報酬の支払い条件でもめた」といった事例は、弁護士が事前にチェックしていれば避けられたケースも多くあります。
社労士に依頼すれば「営業代行と業務委託の線引きが甘く、労働契約とみなされてしまった」といったリスクへの対策も取れるでしょう。
費用はかかるものの、万が一のトラブルによる損失と比べれば、専門家の力を借りるのは十分に合理的な判断です。
不安が残るようであれば、最初だけでも専門家にチェックを依頼してみるのがおすすめです。
まとめ|営業代行と締結する契約書内容を理解すれば、無用なリスクをさけられる
営業代行を依頼する際は、トラブルを未然に防ぐためにも、契約書を締結しておくことをおすすめします。
業務委託契約の基本である「請負契約」と「準委任契約」の違いや、それぞれの契約書(基本契約書・個別契約書)の役割を正しく理解しておくことで、成果の定義や報酬条件、責任の所在が曖昧になるリスクを減らせるでしょう。
テンプレートを活用する場合でも、そのままでは不十分なことが多く、自社の業務内容や契約形態に合わせて調整しなければなりません。
必要に応じて弁護士や社労士などの専門家に相談すれば、より実務に即した安全な契約を結ぶことが可能です。
「なんとなく」の契約で進めず、しっかりと内容を確認・整備してから、営業代行会社との契約締結を進めていきましょう。


-3-400x247.jpg)